CASE STUDY
導入事例
総合研究所・開発部を横断してPoCを実施
社内に点在する資料の活用と知識継承に、STiVを活用した新たなアプローチを模索
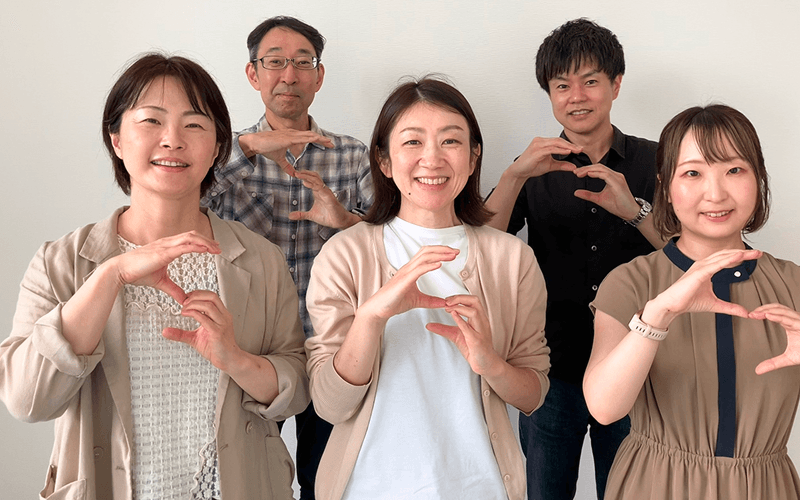
千寿製薬株式会社様 研究開発本部 総合研究所/開発部
- 業種
- 製造業
- 事業内容
- 医薬品の製造・販売
- 従業員数
- 975名(2024年3月31日現在)
千寿製薬株式会社は、眼科領域に特化した医療用医薬品を中心に、独創的で高品質な製品の研究開発・製造・販売を行っている製薬企業です。点眼薬をはじめとした眼科製品で国内外の医療現場を支えながら、新たな治療価値の創出にも継続的に取り組んでいます。
今回は研究開発本部のご担当者様へ資料の活用と知識継承を目的とした、STiVを活用したPoCのお取組みについて、お話を伺いました。
眼科領域に特化した製薬企業として、研究開発現場が直面していた情報アクセスの壁
ー 今回PoCを実施された背景には、どのような課題があったのでしょうか?
研究開発本部の中では、総合研究所と開発部がそれぞれ高度に専門的な業務を行っていますが、共通していたのが「社内に点在する資料や過去の知見にうまくアクセスできない」という悩みでした。
総合研究所では、研究監査対応の際に必要な根拠資料の収集に非常に時間がかかっていました。「どこにどのような資料があるのか」を把握するのに手間がかかり、担当者の経験や記憶に依存している面が大きかったです。また、過去のナレッジや他の研究員の資料を十分に活用できておらず、検索にも時間を要していたため、場合によっては重複してデータを取得することもありました。さらに、各種規制・省令や社内ルールに関する理解や知識のアップデートが追いつかないという課題もあり、根拠資料に基づいて正しい対応を選択できる環境が求められていました。
開発部でも、PMDAからの 照会事項への回答作成のたびに社内資料を一から調査し直す必要があり、効率面に課題を感じていました。回答期限が短く人員も限られる中、膨大な資料から必要な情報を抽出・精査する負荷が大きく、他業務にも支障が生じていました。過去事例の見落としによる再照会リスクもあり、資料収集と再利用の仕組み作りが喫緊の課題でした。迅速な対応を通じ、少しでも早く患者様に治療機会を提供したいという思いも背景にありました。
加えて全社的にDX推進が進められる中、各部門に取り組みテーマが委ねられており、研究開発本部ではナレッジの有効活用や照会事項対応の効率化が課題として挙がりました。こうした背景からSTiVに着目し、タスクフォースの場でも本取り組みを紹介することで、全社DXの中でも先駆け的な位置づけとして取り組みを開始しました。
段階的な検証で、現場に即したユースケースを探る
ー まず短期PoCを実施されたとのことですが、どのような内容で検証されたのか教えてください。
最初の短期PoCでは、総合研究所・開発部から少数のコアメンバーが参加し、STiVの活用可能性をそれぞれの業務に即した形で検証しました。
総合研究所では、社内SOP、CTD文案の根拠資料、規制内容、教育実施の有無などの検索といったユースケースに取り組みました。それぞれ検索の精度には多少のばらつきがあったものの、従来よりも情報に早くたどり着ける感触はあり、活用の可能性を感じました。
開発部では、当局からの照会事項への回答案作成、将来的な照会事項を予測し、回答案をあらかじめ作成する取り組みの2点を検証しました。当局からの照会事項への対応については、過去の資料や事例を効率よく参照できることで、明らかな工数削減につながる感触を得ました。将来の照会事項の予測については、「安全性」や「製造販売後」など照会の対象になりそうな大テーマの予測まではできつつあります。
ー 現在は長期PoCに移行されたと伺いました。進め方や工夫されている点を教えてください。
現在は研究開発本部全体を対象とした長期PoCに移行しています。最初に全参加者向けにSTiVの操作説明会を実施し、各自が自由に自分の業務の中でSTiVを使ってみるスタイルを取っています。
利用状況は定期的にモニタリングし、必要に応じて社内のヘビーユーザーを特定して事例を深掘りしたり、コアメンバーを通じて有効な活用方法を社内に共有したりするなど、利用促進の工夫もしています。ファンリード社には、現場のちょっとした疑問であっても、迅速にチャットで対応いただけており、安心してPoCを進められています。また製薬企業の業務の詳細や、セキュリティや情報の取り扱いの考え方も理解をいただいているので、非常にコミュニケーションがスムーズです。
「社内文書とのつながりやすさ」が決め手に
ー 他の生成AIツールとの比較検討もあったと伺っていますが、STiVを選ばれた理由は何ですか?
STiV を選んだ理由として大きかったのは、RAG※を活用したサービスであり、社内文書のアップロードの手軽さや連携のスムーズさが魅力的だったためです。社内で使っているクラウドストレージサービスと連携しているのですが、そのストレージへのアクセス権限をそのままSTiV側に引き継ぐことができたこともよかったです。
また専門的な用語が多い製薬業界において、自社の文書をそのままAIが理解・咀嚼し、話を飛躍させることなく忠実に正確な情報を返してくれるというRAGの特長も我々にとっては非常に魅力でした。導入時のハードルも比較的低く、業務に自然に取り入れやすい印象でしたね。
※RAG(Retrieval-Augmented Generation、検索拡張生成):
自然言語処理技術の一種であり、外部データソースから関連情報を検索し、それをもとに生成AIが回答を生成する手法。これにより、AIは自身の学習データに依存せず、最新かつ信頼性の高い情報を活用した応答が可能。
PoCの結果を踏まえ、生成AI活用を段階的に前進
ー 現在の手応えや、今後の活用に向けた展望についてお聞かせください。
PoCはまだ継続中ですが、日々の業務の中で各メンバーが実際にSTiVを使ってみることで、「この業務にも応用できそう」「こうすればもっと活かせる」といった発見が生まれてきています。
今後については、PoCの成果をきちんと評価したうえで、本格導入を検討していく予定です。繰り返しになりますが、肌感覚として大きな工数削減に繋がっている業務内容もあるため、業務効率化に繋がりそうかというポイントを評価したいと思います。またSTiVに限らず、生成AIという技術には非常に大きな可能性を感じているので、当社としても今後継続的に活用の幅を広げていきたいと考えています。

